学生からみた社会基盤学科
2025

社会基盤学科で学ぶ学生のみなさんに、学科での生活や、
学問領域としての社会基盤学の魅力についてお聞きしました。
学問領域としての社会基盤学の魅力についてお聞きしました。
- Q1 社会基盤学科に進学した理由を教えてください。
- Q2 社会基盤学科での学生生活を教えてください。
- Q3 社会基盤学科に進学して、新たな学びや発見があれば教えてください。
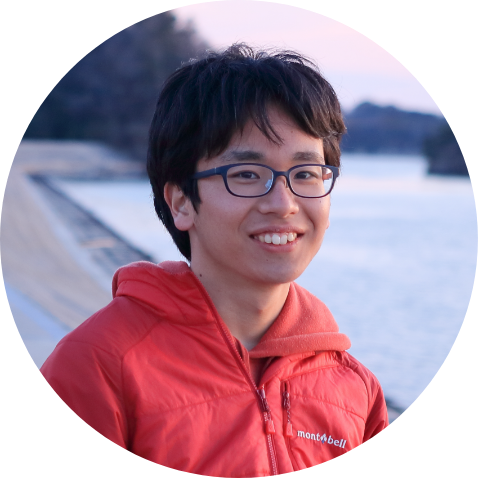
中尾さん
都市と交通G(理科一類→Bコース)
- Q1:高校生の頃から、都市災害やインフラの老朽化といった問題に対して何となく興味を持っていました。
当初は都市工学科を考えていたのですが、駒場のオムニバス授業をきっかけに社会基盤学科にも興味を持ちました。二つの学科は扱う分野も近いように感じられて迷いましたが、デザイン指向の都市工に対して、社基の方が理系の勉強や研究をしっかりできそうで自分に向いているかな、と考えて社基を志望しました。 - Q2:他学科の友人にもよく自慢するのですが、学科仲はとても良いと思います。春休みには、講義で聞いた三陸の復興の様子を見学しよう、ということで学科同期20人で旅行に行ってきました。まちづくりに詳しい同期による解説も付いて、とても充実した旅行になりました。
また、講義のグループワーク以外のタイミングでも、学科同期と真面目な議論をすることができる雰囲気なのは、社基の大きな特徴かもしれないな、と思います。
印象に残った講義としては、加藤先生の国際プロジェクト序論、中井先生の社会基盤史を挙げたいと思います。どちらも、理系の自分が触れてこなかった歴史を扱う講義なのですが、先生方の話がとても面白く、社会基盤学に向き合う上での視野が広がったと感じています。 - Q3:「研究」というものに対するイメージが変わった、というのが一番大きいです。
社基に入るまで、大学での研究というと社会から隔絶されたものという勝手なイメージを抱いていたのですが、社基の研究は社会的な要請があって行われているものが多いし、実地調査に赴いたり学外の人と関わったりする機会も非常に多くあることがわかりました。
3年生で受講した少人数セミナーで、海岸の侵食や液状化などの現地調査に同行し、先生方のお話を聞くことができたことは、工学的な学びになったのはもちろん、将来の研究室生活やその先にある社会基盤の専門家としての働き方のイメージを膨らませるきっかけにもなりました。

上町さん
水圏環境G(文科三類→Aコース)
- Q1:地理、公共政策といったキーワードへの関心から文科三類に進学し、人文系も含め様々な学部学科を検討しました。現象の理解にとどまらず、課題を解決する具体的な方法を導き出し、地域に実装することができるという点に工学の強みを感じ、社基への進学を決めました。もともと水域や地盤といった自然環境と人間社会との相互作用に関心があり、それに関連する防災分野にも興味があったため、それらを研究対象とする研究室との結びつきが強いAコースを志望しました。
- Q2:志に共感しあえる仲間や先生方に出会えたのが何よりの財産だと思っています。文科出身のため、当初は理数系の授業について行けず苦しんだこともありましたが、分からないところを教えてくれたり、自分の強みに気づかせてくれたりする友人や先生方がいたおかげで、この分野にも自分の活躍できる場所があると感じられるようになりました。学生同士で東日本大震災をテーマにスタディツアーを企画・実施するなど、主体的に学びを深めあう雰囲気があり、学びの面でも、人との関わりを通じても、多くの気づきや刺激を得られる環境だと感じています。
- Q3:物理学や法学のように明確に体系化された学問とは異なり、社会基盤の学びは単一の枠組みでは捉えきれない複雑さがあり、当初はその曖昧さに戸惑いを覚えました。しかし、3年生になり実際に地域の人々や関係者と関わりながら課題解決に取り組む中で、実社会の課題は一筋縄ではいかないことを痛感し、多角的な学びの重要性を改めて認識しました。また、もともと構造物に対しては馴染みが薄く、それが進学時の懸念でもありました。しかし学びを深めるにつれ、構造物がただの無機質な存在ではなく、その地域や環境にふさわしい形を目指して考え抜かれた設計がなされていると理解し、興味が深まっていきました。

松村さん
水圏環境G(文科二類→Cコース)
- Q1:そもそも大学で1年半、学部学科選択の猶予を与えられるという理由から東大を志望することを決意し、文科二類の学生として入学しました。教養課程で様々な授業を取る中で、もともと興味のあった都市に関することについてより深く学んでみたいと思うようになり、また演習などを通して学生間の仲が良いという噂も聞いたことを理由に社会基盤学科を選択しました。
- Q2:2年生の夏にとった私の選択は正しかったと胸を張って言えるほど充実した学生生活を送っています。先述しましたように、社会基盤学科はプロジェクトの授業が充実しており、友人たちと切磋琢磨できる環境が整っているように感じます。また、2023年9月から2024年7月までドイツに交換留学に行っていた影響で現在は一つ下の学年と授業を受けたりしていますが、変わらず有意義な時間を過ごすことが出来ています。もちろん、元同期の現M1とも変わらず仲良くしてもらっています笑
- Q3:社会基盤学科は本当に幅広い分野であり、様々なトピックと深く結びついています。だからこそ自分が本当に興味のあるトピックを見つけることが出来ると思います。実際、私も最初は都市のことを学びたいなという漠然とした思いから社基に入りましたが、現在では気候についての研究を始めようとしている最中です。気候と聞くと理学部がやっていることのように思われるかもしれませんが、気候変動の社会へのインパクトに関心があり、それらを予測・制御する必要があると考えると、社基で気候のことをやっているのは不思議ではないと思います。なぜなら社会基盤学科は、社会の根幹にアプローチして社会をよりよくしていくことをミッションとして掲げているのですから。

廣田さん
基盤技術と設計G(理科一類→Aコース)
- Q1:私は元々理系科目(特に数学)が苦手でしたが、専門知識を持って仕事をする理系分野に憧れがあり、英語で点数を稼いで理科一類に入学しました。しかし、線形代数で落単するなど前期教養課程は勉強で苦戦し、難しい数式を扱うような理系分野で自分が生き残っていくのは難しいと感じました。また、実際の社会と結びつく分野に興味があり、かつ人の生死に関わるような非常に社会的にも責任の重い問題と向き合いたいと感じていたため、これらを全て満たす社会基盤分野に興味を持ち、進学しました。実際に進学すると語学力も生かしやすく、私にピッタリだったと感じます。
- Q2:斜面崩壊、水害、地球温暖化など今起こっている問題の科学的な背景を授業で学ぶと、道を歩いていても地形等に注目するようになり、周囲の風景の見え方が変わって楽しいです。学科の雰囲気は先生も周りの友達も打ち解けており、非常に良く、同期とは飲み会をしたり、お笑いを見に行ったりして楽しく過ごしています。先生方は面倒見が良く、チャンスを与えてくださる一方、時間の使い方等は学生に比較的自由にさせてくれます。履修の融通もききやすかったため、サークルとも両立でき、3年生の間は合気道サークルの副将をして、3年生の最後に2段になりました。また、学科の旅費の補助制度を使い、夏休みにアメリカで3週間インターンをしたりと、授業以外でも充実しています。
- Q3:進学前は国際プロジェクトは国際支援を扱い、他の分野はシミュレーションをするのかなというような漠然としたイメージしかありませんでしたが、授業を受けてどの分野も思っていたよりも現地を見るという姿勢を重視していると感じました。AIやシミュレーション等のツールが発達しても、実現象を丁寧に観察するという泥臭い作業はツールを使う際の前提となるものであり、自分の考えを机上の空論で終わらせないためには疎かにできないと強く感じます。私の場合は、授業で能登半島の斜面崩壊現場に行って、地形や土の特性を細かく調べるうちに、土という身近なものが非常に分かりにくい挙動をすることに興味を持ち、地盤分野に進みたいと考えるようになりました。すぐにそれらしい結果・答えが出てもそれに食いつかず、観察力を持って現実を見るという姿勢はたとえ土木分野に残らなくても重要だと思うので、修士卒業までにある程度身につけられたらなと思います。

加藤さん
基盤技術と設計G (理科一類→Cコース)
- Q1:5つあります。
・よく考えたらインフラほど世の中とバランスよく接することが出来る分野は無い。国全体・経済全体に関わる大きな分野で自分の将来を決めることに適した視点を提供してくれそう。
・お遊びではない大規模な国際的な活動がどのようなものか体感したい。
・最も実装の現場に近そう。
・これからのインフラ業界が伸びそうだし、大きな業界だからどこかしら伸びるものが見つけられそう。
・先輩の声を聴いていると、十分にゆとりがあって、やりたければ他のことに挑戦できそう。
・大学で学ぶ意味がありそう。インフラは他のビジネスに比べて国、そして教授たちが実分野で活躍してそう。
・ホームページを見て構成がしっかりしていた。合宿を企画していることなどもあり、歓迎の気持ちが感じられたし、雰囲気も良さそう。
すみません、7個ありました。 - Q2:・印象に残った授業。
応用プロジェクトⅣ・・・橋を3Dプリンターで設計製造、性能(破壊もする)を競い合う。設計と聞くと、授業の延長みたいに感じると思います。しかし、工学の本領でもある、とにかく合意や製造などを何とかする。そういう計算とは違うところで現実が感じられて、悪い意味でもなく純粋に面白い。
課外学習が多い・・・夏の測量合宿や春のマニラでの現場見学など、数えきれないくらい外に出る機会があります。意味のある課外学習がたくさんあるので参加してみてください。
プロジェクト系が多く、知り合い・友達ができて充実しています。 - Q3:社会基盤学、つまり土木は昔からある学問で、既に大事なことは研究しつくされていると思う方もいると思います。実際にはそうでもないのですが、それはさておき、教員も学生も完全に新しくて役に立つことをやるのが当たり前です。中途半端に先端技術だと実用ではなく純粋に偏りがちですが、今のところ「新しくて役に立つことがやりたい?分かった面白そうだからやろう。何が必要なんだ?」という空気感があると感じています。
社会基盤技術の実装戦略という授業で技術の実用化について学び、経営者を交えて議論しました。自分はそこで知ったAster(注:東京大学生産技術研究所の目黒研究室での共同研究発のスタートアップ企業)という企業で長期インターンシップに行きました。そこでよく感じたのは、社会基盤学科の人脈の深さと広さです。深さは国の中枢まで、広さは世界までです。もちろんすべての分野で深く広いとは思いませんが、少なくとも防災研(注:目黒研)の人脈の強烈さを感じました。周りにいるどんな人が居るかは自分の将来の判断にも影響してくるので、重要な発見でした。


